The Hokkaido American Literature Society
日本アメリカ文学会北海道支部
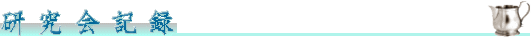
第159回研究談話会 (2012年4月28日、北海道大学)
題目: “Nakeder than Adam and Eve”: Theodicy, Empire, and “Systemless System”
in the New Edition of the Autobiography of Mark Twain
発表:Harold K. Bush, Jr. (Saint Louis University)/司会 久保 拓也(金沢大学)
第158回研究談話会 (2012年3月31日、藤女子大学)
題目: ネイティヴ・スピーカーは誰なのか
――Chang-rae Lee, Native Speaker における英語イデオロギー
発表:伊藤 章(北星学園大学)/司会 皆川 治恵(北海道教育大学)
第157回研究談話会(2012年2月18日、札幌市立大学)
題目:南北戦争ものにおける持続可能性の表象――Robert Penn Warren と Faulkner
発表:松岡 信哉(龍谷大学)/司会 本村 浩二(関東学院大学)
第156回研究談話会 (2012年1月21日、藤女子大学)
題目:「私は流れるものすべてを愛する」
――ヘンリー・ミラー『北回帰線』における流れの場としての身体と都市
発表:井出 達郎(北海道大学大学院)/司会 上西 哲雄(東京工業大学)
2012
第155回研究談話会(2011年11月26日、北海学園大学)
題目:「『白い血』という檻――Go Down, Moses における Issac McCaslin の人種的思考について」
発表:本村 浩二(関東学院大学)/司会 平野 温美
第154回研究談話会(2011年9月10日、札幌市立大学)
題目:『白鯨』の海、棄子の夢
発表:橋本 安央(関西学院大学)/司会 本城 誠二(北海学園大学)
第153回研究談話会(2011年8月27日、札幌市立大学)
題目:Flannery O'Connor の森と街
発表:山口 郁恵(北海道大学大学院)/司会 松井 美穂(札幌市立大学)
第152回研究談話会 (2011年7月23日、北海道大学)
題目:Al Purdy の詩とカナダ
発表:松田 準一(北海道武蔵女子短期大学)/司会 野坂 政司(北海道大学)
第151回研究談話会 (2011年7月2日、藤女子大学)
題目:応用文学の実践──ヘミングウェイとサステナビリティ
発表:瀬名波 栄潤(北海道大学)/
第150回研究談話会 (2011年5月14日、藤女子大学)
題目:Carson McCullers: An Interdisciplinary Conference and 94th Birthday Celebration 参加報告
発表:松井 美穂(札幌市立大学)/
第149回研究談話会 (2011年3月26日、北海学園大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
ヘミングウェイの作品にみる森と先住民
発 表 者:
山口 郁恵 (北海道大学大学院)
コメンテータ:
渡部あさみ (札幌大学女子短期大学部)
コーディネータ:
本荘 忠大 (旭川工業高等専門学校)
2011
第148回研究談話会(2011年1月29日、札幌市立大学)
題目:もうひとつのハーレム・ルネサンス――アロン・ダグラスの世界
発表:寺山佳代子(國學院大学北海道短期大学部)/司会:鎌田 禎子(北海道医療大学)
第147回研究談話会(2010年11月27日、北海学園大学)
題目:移住者にとって演劇とは何か――篠路村烈々布素人芝居の研究
発表:高橋 克依(北星学園大学)/司会:山下 興作(高知大学)
第146回研究談話会(2010年9月18日、札幌市立大学)
題目:John Irving の小説における親子関係と書くという行為
発表:赤間 荘太(北海道大学大学院)/司会:藤井 光(同志社大学)
第145回研究談話会(2010年7月31日、札幌市立大学)
題目:ヘミングウェイと禁酒法──『日はまた昇る』および「ワイオミングのワイン」に見るヘミングウェイの人種意識
発表:本荘 忠大(旭川工業高等専門学校)/司会:片山 厚
第144回研究談話会 (2010年6月19日、藤女子大学)
題目:Taming of the Tomboy and Her Queer Resistance:
Reading the Unspoken Fear/Desire in The Member of the Wedding
マッカラーズの『結婚式のメンバー』再読
発表:松井 美穂(札幌市立大学)/司会 伊藤 章(北星学園大学)
第143回研究談話会 (2010年4月24日、藤女子大学)
題目:正統派ユダヤ教の世界――その思考様式と宗教生活
発表:羽村 貴史(小樽商科大学)/
第142回研究談話会 (2010年3月27日、藤女子大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
“My Visit to Niagara” を読む
発 表 者:
山口 郁恵 (北星学園大学)
原田 智美 (藤女子大学)
コメンテーター:
鎌田 禎子 (北海道医療大学)
司 会:
宮下 雅年 (北海道大学)
2010
第141回研究談話会 (2010年 2月20日、藤女子大学)
題目:不名誉海兵隊員とアメリカの対決:「兵士の故郷」における象徴と嘘
発表:野村 幸輝(旭川大学)/司会:伊藤 義生(藤女子大学)
第140回研究談話会 (2009年11月28日、藤女子大学)
題目:宿命と自由意志――メルヴィルと『失楽園』
発表:平野 温美(北見工業大学)/司会:伊藤 章(北星学園大学)
第139回研究談話会 (2009年 9月12日、藤女子大学)
題目:時の交わる都市――現代LA作家における時間の諸相
発表:藤井 光(同志社大学)/司会:本城 誠二(北海学園大学)
第138回研究談話会(2009年 8月22日、北海学園大学)
題目:食とジェンダー:もう一つの “Big Two-Hearted River”
発表:瀬名波栄潤(北海道大学)/司会:新関 芳生(関西学院大学)
第137回研究談話会 (2009年 7月18日、藤女子大学)
題目:Fitzgerald と空間の比喩――Tender Is the Night における旅と精神分析
発表:井出 達郎(北海道大学大学院)/司会:上西 哲雄(東京工業大学)
第136回研究談話会 (2009年 6月 6日、藤女子大学)
題目:ウイリアム・スタイロン『ナット・ターナーの告白』をめぐる諸問題
発表:小古間甚一(名寄市立大学)/司会:岡崎 清(札幌学院大学)
第135回研究談話会 (2009年3月28日、藤女子大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
主人公は誰か:テネシー・ウィリアムズ『ガラスの動物園』を読み直す
発 表 者:
ファルトゥシナヤ・エカテリーナ (北海道大学大学院)
湯浅 恭子 (北海道大学大学院)
衣川 将介 (北海道大学大学院)
コメンテーター:
高橋 克依 (北星学園大学)
司 会:
山下 興作 (高知大学)
2009
第134回研究談話会 (2009年 1月31日、藤女子大学)
題目:ジャマイカを詩ったクロード・マッケイ――ハーレム・ルネサンスのカリブ文学
発表:寺山 佳代子(國學院短期大学)/司会:本城 誠二(北海学園大学)
題目:日本におけるフランク ・ノリス研究
発表:岡崎 清(札幌学院大学)
第133回研究談話会 (2008年11月29日、藤女子大学)
題目:ヘミングウェイと1930年代のアフリカ──創造されたアフリカ先住民に見るヘミングウェイの人種意識
発表:本荘 忠大(旭川工業高等専門学校)/司会:上西 哲雄(東京工業大学)
第132回研究談話会 (2008年 9月20日、藤女子大学)
題目:“Deep Image” をめぐって──Robert Bly と Jerome Rothenberg
発表:松田 寿一(北海道武蔵女子短期大学)/司会:野坂 政司(北海道大学)
第131回研究談話会 (2008年 8月23日、藤女子大学)
題目:John Steinbeck: The Long Valley 再読──登場人物が抱く願望と不安について
発表:伊藤 義生(藤女子大学)/
第130回研究談話会 (2008年 7月12日、藤女子大学)
題目:逆説の男らしさ──バラク・オバマを読む
発表:瀬名波栄潤(北海道大学)/ 司会:伊藤 章(北星学園大学)
第129回研究談話会 (2008年 6月7日、藤女子大学)
題目:サザン・レディのアイデンティティの問題をめぐって──Eudora Welty の The Optimist's Daughter
発表:本村 浩二(関東学院大学)/ 司会:松井 美穂(札幌市立大学)
第128回研究談話会 (2008年 4月26日、藤女子大学)
題目:アメリカの自然、イギリスの想像力――児童文学を通してみるふたつの国
発表:沢辺 裕子(北海道武蔵女子短期大学)/ 司会:西 真木子(札幌学院大学)
第127回研究談話会 (2008年3月25日、藤女子大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
アメリカでエスニックとして成長すること――現代アメリカ女性作家の3つの短篇を読む
発 表 者:
阿賀 圭祐 (北海道大学)
赤間 荘太 (北海道大学大学院)
松浦 和宏 (北海道大学大学院)
コメンテーター:
渡部あさみ (札幌大学女子短大部)
司 会:
伊藤 章 (北星学園大学)
2008
第126回研究談話会 (2008年 1月26日、藤女子大学)
題目:The Cider House Rules における利己的ミームの支配とマインド・ウイルス
発表:赤間 荘太(北海道大学大学院)/ 司会:本城 誠二(北海学園大学)
第125回研究談話会 (2007年11月10日、藤女子大学)
題目:ハードボイルド・モダニスト――Frances Newman の The Hard-Boiled Virgin、ジェンダー、モダニズム
発表:松井 美穂(札幌市立大学)/ 司会:鎌田 禎子(北海道医療大学)
第124回研究談話会 (2007年9月29日、藤女子大学)
題目:英米ふたつのテッド・ヒューズ像――英国の視点を中心として
発表:熊谷ユリヤ(札幌大学)/ 司会:松田 寿一(北海道武蔵女子短期大学)
第123回研究談話会 (2007年7月21日、藤女子大学)
題目:女性とホロコースト――Cynthia Ozick, The Shawl
発表:羽村 貴史(小樽商科大学)/
第122回研究談話会 (2007年6月23日、藤女子大学)
題目:9・11以降のアメリカ社会の文化変容――その可能性と兆候
発表:伊藤 千晶(北海道大学大学院)/ 司会:伊藤 章(北星学園大学)
第121回研究談話会 (2007年4月28日、藤女子大学)
題目:V・S・ナイポールの作品に見るカリブ諸国とアメリカ
発表:西 真木子(札幌学院大学)/ 司会:沢辺 裕子(北海道武蔵女子短期大学)
第120回研究談話会 (2007年3月24日、藤女子大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
身体性から場所へ、場所から身体性へ 〜アメリカ現代詩を読む〜
発 表 者:
藤井 光 (北海道大学大学院)
赤間 荘太 (北海道大学大学院入学予定)
上村 朋也 (北海道大学大学院入学予定)
司 会:
野坂 政司 (北海道大学)
2007
第119回研究談話会 (2007年1月27日、藤女子大学)
題目:Neil Young が描く Greendale という物語
発表:加藤 隆治(北海道薬科大学)/ 司会:本城 誠二(北海学園大学)
2007
第118回研究談話会 (2006年9月 2日、藤女子大学)
題目:飛躍する生とアイデンティティ――“Red Leaves”にみる「アメリカ」
発表:井出 達郎(北海道大学大学院)/ 司会:片山 厚(北海道大学)
題目:海と森と大平原と――Obasan にみる原型的想像力
発表:伊藤 章(北海道大学)/ 司会:松田 寿一(北海道武蔵女子短期大学)
第117回研究談話会 (2006年7月 8日、藤女子大学)
題目:『響きと怒り』におけるフォークナーの逃避と批判
発表:阿部 与子(北海道大学大学院)/ 司会:本荘 忠大(旭川工業高等専門学校)
第116回研究談話会 (2006年4月22日、北海道大学)
題目:「我々のアメリカ」の彼方に――ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』のクェンティン・コンプソン
発表:井出達郎(北海道大学大学院)/司会:松井美穂(札幌市立大学)
第115回研究談話会 (2006年3月 4日、藤女子大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
アメリカとは何か――ロスト・ジェネレーションに読む
発 表 者:
井出達郎 (北海道大学大学院)
藤田大憲 (北星学園大学大学院)
中野辰彦 (北海道大学大学院)
コメンテーター:
本荘忠大 (旭川工業高等専門学校)
藤井 光 (北海道大学大学院)
司 会:
上西哲雄 (北星学園大学)
第114回研究談話会 (2006年1月14日、北海道大学)
題目:「伝記小説の読み方――Hemingway の The Moveable Feast を例に」
発表:上西哲雄(北星学園大学)/司会:本荘忠大(旭川工業高等専門学校)
2006
第113回研究談話会(2005年9月17日、北海学園大学)
題目:「男らしさ」との格闘――ポストベラム・アメリカとマーク・トウェイン
(Emasculated by Manhood, or Mark Twain as Failure Writer)
発表:久保拓也(金沢大学)
題目:離脱する生に向けて――現代作家における「男」の場合
(Dreaming of An Altogether Different Life: The Case of "Man" in Contemporary Male Writers)
発表::藤井 光(北海道大学大学院)
/司会:久保拓也
第112回研究談話会(2005年6月25日、北海学園大学)
題目:「アメリカ演劇と家族――『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』と『埋められた子供』の場合」
発表:伊藤 章(北海道大学)/司会:松田寿一(北海道武蔵女子短期大学)
第111回研究談話会(2005年4月23日、北海学園大学)
題目:「父の果てへの旅――The Mosquito Coastにおけるマスキュリニティの体制」
発表:藤井 光(北海道大学大学院)/司会:本城誠二(北海学園大学)
題目:「『ビラヴド』再読」
発表:皆川治恵(北海道教育大学岩見沢校)/司会:井上和子(北海道大学)
第110回研究談話会(2005年3月26日、北海学園大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
小説にみられる身体――Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio (1919) のなかの「手」について
発 表 者:
藤田大憲 (北星学園大学大学院)
佐々木有希江 (北海道大学大学院)
桧山 希 (北星学園大学大学院)
司 会:
岡崎 清 (札幌学院大学)
2005
講演会 (2004年10月2日、北星学園大学)
題目:1990 年代以降のアメリカ小説
講師:柴田元幸(東京大学)
第109回研究談話会(2004年 9月18日、 北海道大学)
題目:アメリカの中の二つのアメリカ――Steve Erikson の Arc d'X とあるアメリカ人作家による記憶の追求
発表:井出達郎(北海道大学大学院)/司会:本城誠二(北海学園大学)
講演会 (2004年 9月13日、北海道大学言語文化部)
題目:ウイラ・キャザーの小説について――エロスとタトナスへ
講師:桝田隆宏(高知大学)
第108回研究談話会(2004年 8月28日、 北海道大学)
題目:生存者 David Todd の終りなき任務――Tim O'Brien の July, July
発表:野村幸輝(旭川大学非常勤講師)/司会:岡崎 清(札幌学院大学)
第107回研究談話会(2004年 7月24日、 北海道大学)
題目:女神の影、鯨の腹:『リヴァイアサン』における主体と政治
発表:藤井 光(北海道大学大学院)/司会:高橋克依(北星学園大学)
第106回研究談話会(2004年 6月19日、 北海道大学)
題目:創作の旅――レイモンド・カーヴァー「大聖堂」をめぐって
発表:河野朝子(北海道大学大学院)/司会:松田寿一(北海道武蔵女子短期大学)
第105回研究談話会(2004年 4月17日、 北海道大学)
題目:アメリカの国家と準国家にみるアメリカ的理念――概要とキーワード
発表:伊藤 章(北海道大学)/司会:羽村貴史(小樽商科大学)
第104回研究談話会(2004年 3月 6日、北海学園大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
ジュヴェネッセンスとは:Joyce Carol Oates の“Where Are You Going, Where Have You Been?”を読む
発 表 者:
池田幸恵(北星学園大学大学院)
北谷 潤(北海道大学大学院)
境田 裕(札幌大学大学院)
佐々尾知(北海道教育大学大学院)
Coordinator:
加藤隆治(北海道薬科大学)
野村幸輝(北海道大学大学院)
司 会:
片山 厚(北海道大学)
2004
第103回研究談話会(2003年12月13日、 北海道大学)
題目:手の届かない世界――ポール・オースターの詩をめぐって
発表:藤井光(北海道大学大学院)/司会:本城誠二(北海学園大学)
第102回研究談話会(2003年 8月 2日、 北海道大学)
題目:カーヴァーの詩学――個人的な、あまりにも個人的な
発表:渡辺信二(立教大学)/司会:宮下雅年(北海道大学)
第101回研究談話会(2003年 6月14日、 北海道大学)
題目:自足的世界の魅力と限界――ユードラ・ウェルティの『デルタの結婚式』論
発表:本村浩二(北海道医療大学)/司会:井上和子(北海道大学)
第100回研究談話会(2003年 4月19日、 藤女子大学)
題目:スプリングスティーンの描いたアメリカ
発表:加藤隆治(北海道薬科大学)/司会:本城誠二(北海学園大学)
第99回研究談話会 (2003年 3月 8日、 北海道大学)
題目:ジレンマの時代――エドガー・アラン・ポーの『黒猫』
発表:松田稔(北星学園大学大学院)/司会:鎌田禎子(北海道文教大学)
第98回研究談話会 (2003年 2月22日、北星学園大学)
題目:若手研究者のためのワークショップ
――ペットの死を巡る日米詩を精読・比較する――
司 会:渡辺信二(立教大学)
1. 谷川俊太郎「ネロ――愛された小さな犬に」
Reporter:井出達郎(北海道大学文学部) Commentator:松田稔(北星学園大学大学院)
2. Richard Wilbur,“The Pardon”
Reporter:桑名保智(札幌大学大学院) Commentator:藤井光(北海道大学大学院)
3. John Updike, “he Dog's Death”
担 当:池田幸恵(北星学園大学大学院)
4. Raymond Carver, “Your Dog Dies”
担 当:柴田雅裕(札幌大学大学院)
5. 朗読による詩の音声解釈
講 師:熊谷ユリヤ(札幌大学)
第97回研究談話会 (2003年 1月25日、北海道大学)
題目:『トム・ソーヤの冒険』におけるジェンダー観の策略
発表:金井彩香(北海道大学大学院)/司会:久保拓也(金沢大学)
2003
第96回研究談話会 (2002年12月14日、北海道大学)
題目:ゾロの誕生とその時代
発表:上西哲雄(北星学園大学)/司会:宮下雅年(北海道大学)
第95回研究談話会 (2002年 9月21日、北海道大学)
題目:記憶の書――『最後の物たちの国で』におけるポール・オースターの内的世界
発表:藤井 光(北海道大学大学院)/司会:本城誠二(北海学園大学)
第94回研究談話会 (2002年 7月 6日、北海道大学)
題目:個人史と原爆製造史の接点に生まれた『原子の破片』
発表:吉田かよ子(北星学園大学短期大学部)/司会:羽村貴史(小樽商科大学)
第93回研究談話会 (2002年 4月27日、北海道大学)
題目:ジェーン・コーテスの詩朗読について
発表:野坂政司(北海道大学)/司会:伊藤 章(北海道大学)
第92回研究談話会 (2002年 3月23日、北海道大学)
題目:多文化主義とエコクリティシズムの接点
発表:豊里真弓(札幌大学)/司会:伊藤 章(北海道大学)
第91回研究談話会 (2002年 1月26日、北海道大学)
題目:もうひとりの Sylvia Plath、もうひとつの Ariel――Ted Hughes の Birthday Letters にみる Psychological Drama――
発表:熊谷ユリヤ(札幌大学)/司会:野坂政司(北海道大学)
2002
第90回研究談話会 (2001年 9月22日、北海道大学)
題目:『マウス』のホロコースト表象
発表:羽村貴史(小樽商科大学)/司会:岡崎 清(札幌学院大学)
第89回研究談話会 (2001年 8月25日、北海道大学)
題目:The Diary of Anais Nin にみる日記と女性
発表:渡部あさみ(北海道大学大学院)/司会:瀬名波栄潤(北海道大学)
第88回研究談話会 (2001年 6月23日、北海道大学)
題目:トラウマと許容――ティム・オブライエンの「ウィニペグ」
発表:野村幸輝(北海道大学大学院)/司会:岡崎 清(札幌学院大学)
第87回研究談話会 (2001年 3月24日、北海道大学)
題目:木のイメージについて
――スタフォードの “The Bush from Mongolia” と、矢口以文の「目を覚ましている木」においての比較
発表:中村容子(小樽短期大学)/司会:野坂政司(北海道大学)
第86回研究談話会 (2001年 1月27日、北海道大学)
題目:実在の猫から実在しない猫へ
発表:西村千稔(小樽短期大学)/司会:加藤光男(札幌大学)
2001
To top
第85回研究談話会 (2000年12月16日、北海道大学)
題目:核戦争と終末言説――マラマッド『神の恩寵』考
発表:羽村貴史(小樽商科大学)/司会:上西哲雄(北星学園大学)
第84回研究談話会 (2000年 7月29日、北海道大学)
1. ニューヨーク都市小説としての『アメリカン・サイコ』
発 表:伊藤章(北海道大学)
2. Radical Grooves of Hip-Hop Vernacular――ラップの意味が向かうところ
発 表:本城誠二(北海学園大学)/司会:伊藤 章(北海道大学)
第83回研究談話会 (2000年 6月24日、北海道大学)
1. グローバリゼーション、情報化、ポストモダン都市ニューヨーク
――全国大会シンポジウムの趣旨について
発 表:伊藤 章(北海道大学)
2. 都市の声――Nuyorican Poets Café の詩人たち
発 表:野坂政司(北海道大学)
第82回研究談話会 (2000年 4月22日、北海道大学)
題目:ニューヨーク都市小説としての『虚栄のかがり火』(1987)
発表:伊藤 章(北海道大学)/司会:岡崎 清(札幌学院大学)
第81回研究談話会 (2000年 3月25日、藤女子大学)
題目:100年前の都市小説――ドライサーとボームのまなざし
発表:岡崎 清(札幌学院大学)/司会:小古間甚一(名寄短期大学)
第80回研究談話会 (2000年 1月22日、藤女子大学)
題目:少年が橋を見つける場所――スコット・フィッツジェラルドとティム・オブライエンのフィクション
発表:野村幸輝(北海道教育大学大学院)/司会:伊藤義生(藤女子大学)
2000
第79回研究談話会 (1999年11月27日、札幌大学)
題目:チャーター・スクールにかかわる人々――90年代サンフランシスコ統合学校区の教育改革最前線
発表:鵜浦 裕(札幌大学)/司会:伊藤 章(北海道大学)
第78回研究談話会 (1999年 6月19日、北海道大学)
題目:アメリカ合衆国のふたつの “Passage to India”――Walt Whitman と Alfred T. Mahan
発表:斎藤和夫(札幌大学女子短期大学部)/司会:野坂政司(北海道大学)
第77回研究談話会 (1999年 4月24日、北海道大学)
題目:現代西部の詩人キャスリーン・ノリスとキリスト教西部世界
発表:吉田かよ子(北星学園女子短期大学)/司会:熊谷ユリヤ(札幌大学)
第76回研究談話会 (1999年 3月27日、北海道大学)
題目:拡張主義と19世紀アメリカ美術覚え書き
発表:小川正浩/司会:本城誠二(北海学園大学)
第75回研究談話会 (1999年 1月23日、北海道大学)
題目:『野生の呼び声』における『疎外された労働』
発表:小古間甚一(名寄短期大学)/司会:宮下雅年(北海道大学)
1999
第74回研究談話会 (1998年12月10日、北海道大学)
題目:進化論を拒む人々――現代カリフォルニアにおけるキリスト教創造論運動
発表:鵜浦 裕(札幌大学)/司会:伊藤 章(北海道大学)
第73回研究談話会 (1998年11月28日、北海道大学)
The Trial of the Catonsville Nine について
発 表:高橋克依(北星学園大学)/司会:伊藤 章(北海道大学)
〔 報 告 〕
西村千稔「研究発表の際のタイトルのつけかた」
第72回研究談話会 (1998年 8月 1日、北海道大学)
題目:カナダの日系女性作家――ヒロミ・ゴトーを中心に
発表:井上和子(北海道大学)/司会:野坂政司(北海道大学)
第71回研究談話会 (1998年 7月18日、北海道大学)
題目:冷戦とアメリカ文学
発表:上西哲雄(北星学園大学)/司会:本城誠二(北海学園大学)
第70回研究談話会 (1998年 6月27日、北海道大学)
題目:Asian American Poetry: Similarity and Differences among Chinese, Japanese, and Mixed Heritage Writers
講師:Patrick Murphy(インディアナ大学)/司会:野坂政司(北海道大学)
第69回研究談話会 (1998年 4月25日、北海道大学)
題目:ハードボイルドにおける家族という神話
講師:本城誠二(北海学園大学)
第68回研究談話会 (1998年 3月25日、北海道大学)
題目:This is a BaddDDD Paper
発表:Diane Cammarata(小樽商科大学)
第67回研究談話会 (1998年 1月31日、北海道大学)
題目:A Japanese Robinson Crusoe――小谷部全一郎のアイヌ教育と19世紀の日米関係
発表:矢口祐人(北海道大学)
1998
第66回研究談話会 (1997年12月20日、北海道大学)
題目:アメリカ文学とロック
発表:加藤隆治(藤女子大学非常勤講師)
第65回研究談話会 (1997年 7月19日、北海道大学)
題目:Primitive Hemingway: Native Americans in Short Stories (In Our Time を中心に)
発表:藤原大輔(北海道大学大学院)
第64回研究談話会 (1997年 3月29日、北海道大学)
題目:ハックルベリー・フィンにおける男性化教育――試論と考察
発表:久保拓也(北海道大学大学院)/司会:瀬名波栄潤(北海道大学)
1997
第63回研究談話会 (1996年12月21日、北海道大学)
題目:William Staford の詩の一面
発表:松田寿一(札幌北高等学校)
第62回研究談話会 (1996年 7月13日、北海道大学)
題目:Saul Bellow の “Two Morning Monologues” について
発表:加藤隆治(札幌大学非常勤講師)
第61回研究談話会 (1996年 6月 1日、北海道大学)
題目:Maxine Hong Kingston, The Woman Warrior を中心に
発表:井上和子(北海道大学)
第60回研究談話会 (1996年 3月23日、北海道大学)
題目:チャイニーズ・アメリカン・マンフッドを求めて
――フランク・チンとチャイニーズ・アメリカン・アイデンティティの再構築
発表:伊藤 章(北海道大学)
第59回研究談話会 (1996年 1月27日、北海道大学)
題目:チャールズ・ロングフェローの物見遊山――1871年秋の東北見聞記の紹介と解説
発表:矢口祐人(北海道大学)
1996
第58回研究談話会 (1995年12月16日、北海道大学)
題目:Amy Tan, The Kitchen God's Wife について
発表:皆川治恵(北海道教育大学)
講演会 (1995年10月2日、札幌アメリカン・センター)
題目:自作を語る
講師:バーラティ・ムーカジ(作家)/司会:宮下雅年(北海道大学)
第57回研究談話会 (1995年 9月30日、北海道大学)
題目:Israel Zangwill の Melting-Pot を読む
発表:岡崎 清(札幌学院大学)
第56回研究談話会 (1995年 6月24日、北海道大学)
題目:Bharati Mukherjee, Jasmine について
発表:宮下雅年(北海道大学)
講演会 (1995年 6月22日、札幌アメリカン・センター)
題目:自作を語る
講師:オスカー・イフェロス(作家)/司会:皆川治恵(北海道教育大学)
講演会 (1995年 6月 5日、札幌アメリカン・センター)
題目:多文化主義と変化するアメリカ文学の序列
講師:ポール・ローター(トリニティ大学)
題目:移民と文化的変化
講師:ドリス・フリーデンソン(ジャージー・シティ州立大学)
司会:加藤光男(札幌大学)
第55回研究談話会 (1995年 4月15日、北海道大学)
題目:いま、なぜアジア系アメリカ文学か――アジア系アメリカ文学に関する共同研究の呼び掛け
発表:伊藤 章(北海道大学)
第54回研究談話会 (1995年 2月 4日、北海道大学)
題目:Unpublished, Perished Achivements: From The Calms of Capricorn
発表:片山 厚(北海道大学)
1995
第53回研究談話会 (1994年12月17日、藤女子大学)
題目:Jack London と超人主義
発表:小古間甚一(市立名寄短期大学)
第52回研究談話会 (1994年 9月17日、北海道大学)
題目:ナサニエル・ホーソンの『緋文字』について――3つのさらし台のシーンを中心にして
発表:松田奏保(北海道大学大学院)
第51回研究談話会 (1994年 8月27日、北海道大学)
題目:Adventures of Huckleberry Finn について――Huckの思考と判断の過程
発表:久保拓也(北海道大学大学院)
第50回研究談話会 (1994年 6月18日、北海道大学)
題目:職業としての建築と人間の経験世界
発表:フィリップ・シール(札幌市立高等専門学校)
講演会 (1994年 6月 2日、札幌アメリカン・センター)
題目:鷲と日のはざまで――日本とアメリカへの個人的感想
講師:Ihab Hassan(ウィスコンシン大学)/司会:江草久司(藤女子大学)
第49回研究談話会 (1994年 5月14日、北海道大学)
題目:“The Paradise of Bachelors and the Tartarus of Maids” にみる資本主義
発表:相原成史(稚内北星学園短期大学)
第48回研究談話会 (1994年 3月26日、北海道大学)
題目:William Cullen Bryant と Hudson River School
発表:小川正浩(増毛高等学校)
第47回研究談話会 (1994年 1月29日、北海道大学)
題目:American Nature Writing: The Thoreauvian Traditions
発表:Scott Slovic (フルブライト招聘講師)
1994
第46回研究談話会 (1993年12月11日、北海道大学)
題目:Nick Adams の感覚と行動――Ernest Hemingway の Big Two-Hearted River を中心にして
発表:新関芳生(北海道大学大学院)
講演会 (1993年 9月27日、札幌アメリカン・センター)
題目:アジア系アメリカ文学とフランク・チンの描く世界
講師:フランク・チン(作家)/司会:伊藤 章(北海道大学)
第45回研究談話会 (1993年 7月17日、北海道大学)
題目:Edgar Allan Poe の短編について――信頼できない語り手と無知な語り手
発表:鎌田禎子(北海道大学大学院)
第44回研究談話会 (1993年 6月26日、北海道大学)
題目:アメリカ現代詩とカリブ海的要素
発表:野坂政司(北海道大学)
第43回研究談話会 (1993年 3月26日、北海道大学)
題目:William Saroyan 文学の特質――“The Pomegranate Trees” を中心に
発表:江草久司(藤女子大学)
第42回研究談話会 (1993年 1月23日、北海道大学)
題目:ジョン・スミスとチュサピーク湾コロニー
発表:菊池 昭(小樽商科大学)
<北海道アメリカ学会>
1993
第41回研究談話会 (1992年12月 5日、北海道大学)
題目:John Smith 異聞――Leslie A. Fiedler の『アメリカ文学の原型』論をめぐって
発表:菊池 昭(小樽商科大学)
第40回研究談話会 (1992年11月21日、北海道大学)
題目:現代黒人女性作家による奴隷小説
――Sherley Anne Williams の Dessa Rose とToni Morrison の Beloved を中心に
発表:皆川治恵(北海道教育大学)
第39回研究談話会 (1992年10月 2日、北海道大学)
題目:Faulkner におけるキリスト像について
発表:渡辺一郎(静修女子短期大学)
題目:“Two Rivers” の Vision――Emerson の Platonism
発表:和氣久明(苫小牧高等専門学校)
講演会 (1992年 9月 8日、札幌アメリカン・センター)
題目:異文化の対立
講師:Chaim Potok(作家)/司会:片山 厚(北海道大学)
第38回研究談話会 (1992年 8月22日、北海道大学)
題目:虚構の演劇としての『ガラスの動物園』
発表:山下興作(高知大学)
第37回研究談話会 (1992年 5月 2日、北海道大学)
題目:アメリカ演劇とリアリズム――なぜアメリカ演劇は現代においてもリアリズムが主流なのか
発表:伊藤 章(北海道大学)
第36回研究談話会 (1992年 3月14日、北海道大学)
題目:贋金と19世紀アメリカ文学――The Memoirs of Stephen Burroughs を皮切りに
発表:宮下雅年(北海道大学)
講演会 (1992年 1月28日、札幌アメリカン・センター)
題目:私、そして小説
講師:Jeanne Wakatsuki Houston(作家)/司会:川瀬裕子(札幌学院大学)
1992
第35回研究談話会 (1991年12月21日、北海道大学)
題目:“Bartleby” について
発表:土永 孝(北海道大学)
第34回研究談話会 (1991年10月19日、北海道大学)
題目:ベローの<博士論文>――『犠牲者』を読む
発表:杉野健太郎(広島大学)
題目:“The Capital of the World” を読む
発表:田代 真(帯広畜産大学)
第33回研究談話会 (1991年 9月28日、北海道大学)
題目:モダニズム検証――1. 序論 2. モダニズムのアメリカ詩 3. モダニズムとアメリカ演劇
発表:江草久司(藤女子大学)/伊藤 章(北海道大学)
第32回研究談話会 (1991年 6月29日、北海道大学)
題目:物語のあとに来るもの――語られぬ世界を旅して
発表:伊藤義生(藤女子大学)
第31回研究談話会 (1991年 5月25日、北海道大学)
題目:“haunted house”――女性と創造力――エミリ・ディキンソンを中心に
発表:井上和子(北海道大学)
講演会 (1991年 4月22日、札幌アメリカン・センター)
題目:ケネス・コーク自作の朗読と解説
講師:Kenneth Koch(詩人)/司会:矢口以文(北星学園大学)
講演会 (1991年 3月25日、札幌アメリカン・センター)
題目:アリス・ウォーカーの短篇小説
講師:Alice H. Petry(Rhode Island School of Design)/司会:井上和子(北海道大学)
第30回研究談話会 (1991年 3月16日、北海道大学)
題目:自伝論の試み――事実と虚構の間
発表:伊藤 章(北海道大学)
第29回研究談話会 (1991年 1月26日、北海道大学)
題目:エマソンのプラトニズム
発表:和氣久明(苫小牧工業高等専門学校)
1991
To top
第28回研究談話会 (1990年12月25日、北海道大学)
題目:『エデンの東』のキャシー・エイムズについて
発表:加藤光男(札幌大学)
第27回研究談話会 (1990年10月13日、北海道大学)
題目:Jack London の “pastoral paradise”
発表:岡崎 清(東京理科大学)
題目:Jackson MacLow の詩的戦略について
発表:野坂政司(北海道大学)
講演会 (1990年10月 5日、札幌アメリカン・センター)
題目:現代のアメリカ詩
講師:David Lehman(詩人)/司会:野坂政司(北海道大学)
講演会 (1990年 9月25日、札幌アメリカン・センター)
題目:フォークナーとミシシッピー
講師:Noel Polk(南ミシシッピ−大学)/司会:渡辺一郎(静修短期大学)
第26回研究談話会 (1990年 7月14日、北海道大学)
題目:闇との出会い――ホーソンの未完の物語における自伝性
発表:Celeste Loughman(大阪大学フルブライト招聘講師)
第25回研究談話会 (1990年 6月23日、北海道大学)
題目:感覚的なものと精神的なものの関わり――Ahab における
発表:新関芳生(北海道大学大学院)
講演会 (1990年 6月 1日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカ文学の危機
講師:James Salter/司会:片山 厚(北海道大学)
第24回研究談話会 (1990年 4月21日、北海道大学)
題目:Faulkner の The Sound and the Fury 試論
発表:松井美穂(北海道大学大学院)
講演会 (1990年 4月12日、札幌アメリカン・センター)
題目:メアリー・モリスの世界
講師:Mary Morris/司会:川瀬裕子(札幌学院大学)
第23回研究談話会 (1990年 3月13日、北海道大学)
題目:The Scarlet Letter について
発表:池田志郎(熊本大学)
第22回研究談話会 (1990年 1月16日、北海道大学)
題目:The American Transcendentalism について
発表:David Cody(北海道大学フルブライト招聘講師)
1990
第21回研究談話会 (1989年12月16日、北海道大学)
題目:A Touch of the Dramatist、詩人、そしてE・オニール
発表:片山 厚(北海道大学)
第20回研究談話会(1989年11月25日、小樽女子短期大学)
題目:William Styron の “The First Day of School” を読む
発表:西村千稔
講演会 (1989年10月16日、札幌アメリカン・センター)
題目:Melvilleを語る
講師:Harrison Hayford & Hershel Parker/司会:David Cody(北海道大学)
第19回研究談話会 (1989年10月 7日、北海道大学)
題目:Here, Now, Involuntary Feelings――Bellow, Seize the Day 論
発表:杉野健太郎(駒沢大学苫小牧短期大学)
第18回研究談話会 (1989年 7月22日、北海道大学)
題目:Bartleby の存在感
発表:綾部史夫(北海道教育大学)
講演会 (1989年 7月12日、札幌アメリカン・センター)
題目:T. Coraghessan Boyle 自作朗読会
講師:T. Coraghessan Boyle/司会:野坂政司(北海道大学)
第17回研究談話会 (1989年 6月10日、北海道大学)
題目:フォークナーにおける光と影
発表:渡辺一郎(静修短期大学)
朗読会 (1989年 5月29日、北星学園大学)
講師:ジョン・アシュベリ/矢口以文(北星学園大学)
講演会 (1989年 5月19日、札幌アメリカン・センター)
題目:現代のアメリカ短篇小説
講師:ウィリアム・ギャス/司会:片山 厚(北海道大学)
第16回研究談話会 (1989年 4月22日、北海道大学)
題目:万華鏡的調和――ホイットマンの人間像
発表:稲垣春男(静修短期大学)
第15回研究談話会 (1989年 3月25日、北海道大学)
題目:文学における時間をめぐって
発表:本城誠二(北海学園大学)
第14回研究談話会 (1989年 2月18日、北海道大学)
題目:詩的メタファーの記号論――Blake の “London” をめぐって
発表:宮町誠一(小樽女子短期大学)
1989
第13回研究談話会 (1988年12月17日、北海道大学)
題目:日系アメリカ人作家について
発表:川瀬裕子(札幌学院大学)
第12回研究談話会 (1988年11月26日、北海道大学)
題目:Hawthorne の “Rappaccini's Daughter” について
発表:木村信一(北星学園大学)
講演会 (1988年11月14日、札幌アメリカン・センター)
題目:佇む私――作家自身が創作について語る
講師:アン・ビーティ/司会:伊藤 章(北海道大学)
第11回研究談話会 (1988年10月 8日、北海道大学)
題目:Steinbeck の Of Mice and Men について
発表:江草久司(藤女子大学)
第10回研究談話会 (1988年 6月18日、北海道大学)
題目:W. Styron の小説にみられる悲劇的主人公の考察
発表:岡崎 清(東京理科大学)
講演会 (1988年 6月 1日、札幌アメリカン・センター)
題目:1980年代アメリカにおけるジョン・スタインベックの評価
講演:テツマロ・ハヤシ(ボール州立大学)/司会:江草久司(藤女子大学)
第9回研究談話会 (1988年 4月23日、北海道大学)
題目:ポストモダニズム以後の諸問題
発表:鶴見精二(小樽商科大学)
第8回研究談話会 (1988年 3月26日、北海道大学)
題目:ジェイムズあれこれ
発表:伊藤千秋(武蔵女子短期大学)
第7回研究談話会 (1988年 1月30日、北海道大学)
題目:窓の内と外――T. S. Eliot の Ash-Wednesday
発表:中村敦志(札幌学院大学)
1988
第6回研究談話会 (1987年12月 5日、北海道大学)
題目:ロバート・フロストの視点
発表:金山勝也(国学院女子短期大学)
第5回研究談話会 (1987年 9月26日、北海道大学)
<支部シンポジウム>
司会:菊池 昭(小樽商科大学)
講師:伊藤 章(北海道大学)
講師:木村淳子(武蔵女子短期大学)
講師:伊藤仙一(北海道教育大学旭川分校)
第4回研究談話会 (1987年 7月18日、北海道大学)
題目:作品研究と伝記的資料――作品の理解のために伝記は不可欠なものなのだろうか
発表:伊藤 章(北海道大学)
第3回研究談話会 (1987年 4月18日、北海道大学)
題目:『サンクチュアリ』中のポパイ挿話をめぐって――フォークナーの想像力と伝記的事実――
発表:菊池 昭(小樽商科短期大学)
第2回研究談話会 (1987年 1月31日、北海道大学)
題目:“A Rose for Emily” を読む――視線を中心に
発表:池田志郎(札幌学院大学)
第1回研究談話会 (1986年12月13日、北海道大学)
題目:登場人物の変名をめぐって――The Member of the Wedding と The Catcher in the Rye を中心に――
発表:宮下雅年(北海道大学)
詩の朗読の会1986年4月11日、札幌アメリカン・センター)
講師:Donald Hall/司会:矢口以文(北星学園大学)
1986
講演会 (1985年 8月 1日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカ文学に映る都市像
講師:Alan Trachtenberg(イェール大学)/司会:片山 厚(北海道大学)
講演会 (1985年 4月23日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカの大衆文化――その神話と象徴
講師:Richard P. Horwitz(アイオワ大学)/司会:片山 厚(北海道大学)
講演と詩の朗読会(1984年 9月7日、札幌アメリカン・センター)
講師:William Stafford/司会:矢口以文(北星学園大学)
講演会 (1984年 4月17日、札幌アメリカン・センター)
題目:私の小説と創作プロセス
講師:David H. Bradley/司会:江草久司(藤女子大学)
講演と朗読の会 (1983年12月 6日、札幌アメリカン・センター)
講師:Maxine Kumin/司会:矢口以文(北星学園大学)
講演会 (1983年10月18日、札幌アメリカン・センター)
題目:ハイフンつきのアメリカ作家
講師:Daniel Aaron(ハーヴァード大学)/司会:片山 厚(北海道大学)
講演会 (1983年 2月 9日、札幌アメリカン・センター)
題目:ヘミングウェイの心の葛藤――ミシガン時代
講師:Lawrence Ivan Berkove(ミシガン州立大学)
講演会 (1982年10月14日、札幌アメリカン・センター)
題目:脱工業化社会におけるさまざまな異端の形態について
講師:Ihab Hassan(ウィスコンシン大学)/司会:矢口以文(北星学園大学)
特別講演会 (1981年 2月27日、札幌アメリカン・センター)
題目:文学と心理学
講師:鈴木重吉(札幌商科大学)
1981
To top
特別講演会 (1980年 8月21日、札幌アメリカン・センター)
題目:The Self in Writing: Recent American Criticism
講師:Norman N. Holland(ニューヨーク州立大学)
講演会 (1980年 7月 9日、札幌アメリカン・センター)
題目:戦後アメリカのユダヤ人
講師:Raymond Federman(ニューヨーク州立大学)
定例研究会 (1979年 1月30日、札幌アメリカン・センター)
題目:ジーン・トゥーマ:Cane から Winter on Earth and Other Stories へ
発表:寺山佳代子(三愛女子高等学校)/司会:田中育造(北星学園大学)
定例研究会 (1978年12月14日、札幌アメリカン・センター)
題目:Anne Sexton の詩の空間
講師:木村淳子(武蔵女子短期大学)/司会:江草久司(藤女子大学)
定例研究会 (1978年 9月21日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカ文学に見られる女性
講師:井上和子(北海道大学)/司会:川瀬裕子(札幌商科大学)
定例研究会 (1978年 5月18日、札幌アメリカン・センター)
題目:Poetry of Galway Kinnell
発表:S. L. Toakar(北星学園大学)/司会:矢口以文(北星学園大学)
講演会 (1978年 4月28日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカ現代詩朗読の夕
講師:Kenneth Rexroth & Morgan Gibson/解説:矢口以文(北星学園大学)
<共催:アメリカン・センター>
1978
定例研究会 (1977年11月17日、札幌アメリカン・センター)
題目:現代黒人文学の動向
発表:江草 久司 (藤女子大学)/司会:田中 育造 (北星学園大学)
講演会 (1977年 9月22日、札幌アメリカン・センター)
題目:作家と社会
講師:William H. Gass/司会:片山 厚 (北海道大学)
<共催:アメリカン・センター>
講演会 (1977年 7月11日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカの現代演劇:オフ・ブロードウェイとその他の演劇活動
講師:Kenneth Jones/司会:高久 真一 (北海道大学)
<共催:アメリカン・センター>
講演・定例研究会(1977年 2月 3日、札幌アメリカン・センター)
題目:あたらしい文化を築くアメリカ女性詩人たち
講師:渥美 育子 (青山学院大学)/司会:井上 和子 (北海道大学)
題目:ケネス・バークの言語観――『宗教の修辞学』を中心に
発表:倉田 恵介 (札幌短期大学)/司会:板垣 憙 (藤女子大学)
<共催:アメリカン・センター>
1977
定例研究会 (1976年11月 9日、札幌アメリカン・センター)
題目:私のアメリカ
発表:井上 和子 (北海道大学)/司会:川瀬 裕子 (札幌短期大学)
講演会 (1976年10月25日、札幌アメリカン・センター)
題目:What Makes American Literature American.
講師:Charles Anderson/司会:伊藤 仙一 (北海道教育大学旭川分校)
<共催:アメリカン・センター>
講演会 (1976年 9月 9日、札幌アメリカン・センター)
題目:現代アメリカ文学について
講師:William Gaddis/司会:板垣 憙 (藤女子大学)
<共催:アメリカン・センター>
講演会 (1976年 5月13日、札幌アメリカン・センター)
題目:翻訳について
講師:小林 謙一 (北海道武蔵女子短期大学)/司会:北市 陽一 (北海道大学)
講演会 (1976年 4月27日、札幌アメリカン・センター)
題目:詩人ロバート・クリーリを囲む会
講師:Robert W. Creeley/司会:矢口 以文 (北星学園大学)
1976
定例研究会 (1975年12月11日、札幌アメリカン・センター)
題目:Young American Poets
発表:矢口 以文 (北星学園大学)/Robert Kuntz (北星学園大学)
講演会 (1975年10月28日、札幌アメリカン・センター)
題目:ユージン・オニールからエドワード・オルビーまで
講師:Horst Frenz(インディアナ大学)/司会:片山 厚 (北海道大学)
<共催:アメリカン・センター>
講演会 (1975年10月15日、札幌アメリカン・センター)
題目:アメリカ詩人を囲む会
講師:Lucien H. Stryk(北イリノイ大学)/司会:矢口 以文 (北星学園大学)
<共催:アメリカン・センター>
定例研究会 (1975年 9月30日、札幌アメリカン・センター)
題目:最近のアメリカ事情
発表:阿部 晃夫 (東海大学)/司会:田中 育造 (北星学園大学)
定例研究会 (1975年 4月22日、札幌アメリカン・センター)
題目:文学における悲劇的人物について――フォークナーの作品を中心にして
発表:菊池 昭 (小樽商科大学)
講演会 (1975年 4月11日、札幌アメリカン・センター)
題目:Poetry Reading
講師:谷川俊太郎 & Kenneth Rexroth/司会:金関 寿夫 (東京都立大学)
定例研究会 (1975年 2月26日、札幌アメリカン・センター)
題目:Free Discussion:J. C. Oates の “The Plot” について
司会:片山 厚 (北海道大学)
講演会 (1975年 2月20日、札幌アメリカン・センター)
題目:Contemporary Jewish-American Fiction
講師:Stanley Schatt/司会:田中 育造 (北星学園大学)
<共催:アメリカン・センター>
1975
定例研究・講演会(1974年12月13日、札幌アメリカン・センター)
The Hungry Ghosts をめぐるさまざまのヴィジョン
発 表:片山 厚 (北海道大学)
〔 講 演 〕
題目:アメリカの大学風景
講師:鈴木 重吉 (北海道大学)/司会:伊藤 千秋 (北海道教育大学札幌分校)
講演会 (1974年11月22日、札幌アメリカン・センター)
題目:The Fear of Beauty in American Literature
講師:Jack H. Gilbert/司会:片山 厚 (北海道大学)
<共催:アメリカン・センター>
講演会 (1974年 9月21日、札幌アメリカン・センター)
題目:1970年代のアメリカ作家論
講師:John Gardner/司会:刈田 元司 (上智大学)
<共催:アメリカン・センター>
定例研究会 (1974年 9月 4日、札幌アメリカン・センター)
題目:Free Discussion:黒人作家の文学について――James Baldwin の作品を中心に
発表:田中 育造 (北星学園大学)
定例研究会 (1974年 6月25日、札幌アメリカン・センター)
1. O'Neill 劇における都会・田園・海洋そしてユートピア――安住の地を求めるヒーローの群れ
発 表:伊藤 章 (北海道大学大学院)
2. Flannery O'Conner の “The Artificial Nigger” について
発 表:川瀬 裕子 (札幌短期大学)/司会:真柳 節 (北星学園女子短期大学)

